
ここは夢園荘LastStory
BEGINNING
第5話
夜10時。
夏樹は『NAC ROOM』でデザインの下描きを5枚ほど上げていた。
真治が来る前は描いては消しを繰り返していた割りに、乗ると仕事の速い夏樹であった。
「このペースなら帰れ……ないか……」
時計を見て諦めたらしい。
溜め息を一つ付くと、手元のカップを持って立ち上がり、部屋に備え付けのコーヒーサーバーからコーヒーを注いだ。
そして一口飲んだとき、携帯電話の音。
夏樹はこんな時間に誰だろうと思いながら、携帯の液晶を見ると家からだった。
「?」
不思議に思いながら電話に出る。
『夏樹〜!』
電話口から聞こえる真治の声。
「な、親父!?」
『恵理はずいぶんと良い奥さんしてるじゃないか。
卒業なんて待たずにとっとと結婚して子供を作ったらどうだ』
「なんで、親父が家にいるんだよ!」
『天候不良で欠便になってな。でまぁホテルは取ったから良いんだが、物のついでだと思ってな』
「天候不良? この部屋に窓が無いからいい加減なこと言って……」
『分かったか?』
「分かる」
『そうか……勘がいいな』
「そう言う問題じゃないだろ。どうせ最初からその目的だったんだろ」
『当たり』
夏樹はこめかみに指を当てながら怒りを堪えた。
恐らく電話の向こうの親父の後ろで恵理が複雑な表情をしているだろう。
「それで何のようだ。親父のお陰で帰れそうもないからな」
『せっかちな奴だな……ま、いいか。
さっき言い忘れたんだが、そろそろ考えてみたらどうだ』
「考えろって……あのことか……」
『ああ』
「もう少し時間をくれると嬉しいんだけどな」
『そうか。だがそろそろ決めても良いと思うんだが』
「そうだな……」
『用事はそれだけだ』
「親父、とっととホテルに戻れよ。
恵理だって明日学校があるんだから」
『分かってる。
今、恵理に変わるな』
しばしの無音、そして恵理の声。
『夏樹さん、お仕事中にごめんね。お義父様がどうしてもって……』
「恵理は気にしなくて良いから」
『うん』
「とにかく明日に支障をきたすといけないから、早く親父には帰ってもらって戸締まりして寝るんだぞ」
『うん、分かった。
それじゃ、お仕事頑張ってね』
「ああ」
『お休みなさい』
「お休み」
そして静かに切れる電話。
夏樹は切れた携帯を暫し見つめた。
「……何やってるんだ、親父は?」
夢園荘の前に黒塗りのハイヤーが止まっていた。
運転手はあくびをしながら乗せてきた人を待っているようだ。
その101号室、管理人室兼『早瀬夏樹と樋山恵理の愛の巣』(友人達の間でこう言われている)の玄関で真治が帰ろうと靴を履いているところであった。
「長居をして済まなかったね」
「いえ、そんなことはありません。いつでもいらしてください」
「ありがとう。今度来るときは夕子と新しく生まれる娘を連れて来るから」
「楽しみにしてます」
「ところで本当に子供はまだなのかい?」
「ま、まだです」
真治が真面目な顔で聞くと、恵理は顔を真っ赤にして俯きながら小さく答えた。
「私も夕子も早く孫の顔が見たくて楽しみにしてるんだよ」
「は、はぁ……」
「ではまたね」
真治はそう言うとドアを開けて外に出た。
「そこまで見送ります」
「良いから良いから、すぐそこに車を待たせてあるんでね」
「そうですか?」
「ああ、ではまた」
「はい」
そう言いながら真治は外側からドアを締め、外で待たせてある黒塗りのハイヤーに乗り込んだ。
そして運転手と2、3言葉を交わすと車は彼が宿泊しているホテルに向けて出発した。
玄関で見送った恵理はそのまま鍵をかけ、リビングに戻ると真治に出したコップを台所に持っていった。
コップを簡単に洗い、水切りの食器入れに入れると再びリビングに戻る。
そして疲れたように座り込み、テーブルに突っ伏した。
「緊張した〜」
テーブルの脇には教科書とノートと筆記用具がまとめて積んである。
真治はテレビを見ながら宿題をしていたところに訪ねてきたらしく、恵理は相当慌てて対応したようだ。
しばらく突っ伏した形で止まっていたが、思い出したように頭を上げテレビの上の写真立てを見た。
そこには夏に保養施設にみんなで行った時に、夏樹とツーショットで撮った写真が入っている。
「子供か……早く欲しいな……」
するとパッと体を起こし鞄からスケジュール帳を取り出す。
そしてシャープペンシルを片手になにやら書き込み始める。
「そっか……」
そうつぶやくとスケジュール帳を眺めながら何故か嬉しそうな顔になっていた。
少しだけ時間を戻して夜9時。
喫茶ノルン店内。
卯月は住居の方へと戻り、店内では高志が閉店作業を終えゴミをまとめている。
この駅前周辺は早朝の鳥害を避けるため、深夜のゴミ収集を実施していた。
「ゴミを捨ててくる」
「は〜い」
住居の方から卯月の声。
それを聞くと高志は裏口から出て、ゴミ集積場にゴミを置きに行った。
商店街のはずれにあり集積所は歩いて数分程度。
「卯月をどこかに連れて行ってやりたいけど、定休日が平日だからそうもいかないよな……」
ゴミを片手に小声で独り言を言いながら、高志は昨日の夏樹と恵理のこと思い出していた。
「考えてみれば夏樹って半分自由業だもんな。時間は空いてるわけだし、少しだけ羨ましいな」
噂の夏樹は現在本社で缶詰になっていることも知らずに羨んでいる高志であった。
そうこう歩いていると、集積場に着きそこにゴミを置いたとき、当たりがあまりに静かなことに気づいた。
静かと言うよりは無音と言う方が正解だろう。
この集積場は先にも書いたとおり、商店街のはずれにあるため人通りなどほとんど無い。
それでも裏道にある飲み屋などや駅からの帰宅する人たちなどで、この時間も通りから人の声などが聞こえてくる。
しかし、それが無いのだ。
高志は急いで商店街の大通りに戻る。
だが、いつもならいるはずの人々の姿も無かった。
「どういう事だ……」
高志は目を細め当たりの伺う。
そして360度ぐるりと見回すとある一点を見つめた。
「出てきたらどうだい?」
その声に建物の影から一組男女が姿を見せた。
一見普通の兄妹のように見える二人組だが、高志はこの二人から得も知れぬ気配を感じていた。
男の方は年の頃は17、8歳、身長180cm前後で何処にでもいる感じの若者だ。
だが特徴として腰まで届く長い髪を襟元で無造作に縛っている。
少女の方は15歳前後で身長は150cm前後。
美少女の部類に入る容姿をしている。
「誰にも迷惑をかけたくないからこのあたり一体に結界を張らせてもらった」
青年は簡単に説明する。
「結界? それで人が誰もいないって事か」
「そういうことだ」
「目的は?」
「君の持つ『煌玉』を貸して欲しい」
「こう……ぎょく……?」
「分からないか……恐らく別の名前で呼んでいるのだろうな……」
青年は一人納得したように頷くが、高志はその言動があまりに人をバカにしているように思え切れそうになっていた。
「青風、それじゃ相手に伝わらないよ」
その時、青年の横に立っていた少女が口を開いた。
「ごめんね、青風って口べたなの。
青風って言うのはこの人の名前。それで私はエア、よろしくね」
底抜けに明るい少女の自己紹介は、その場の緊張感を一気に解きほぐしたように感じられた。
「はぁ……」
「エア……もう少し緊張感というものが……」
「そんな事言っていたら、まとまる物もまとまらないでしょ」
「そうか?」
「そうだよ」
(な、何なんだ、この二人は?)
さっきまでの緊迫とした空気が何処に行ったのか、高志はただただ二人の会話を唖然として眺めていた。
「それで用件なんだけど」
エアはまるで怯える子供をあやすような優しい口調で高志に語りかけた。
だがその内容は先ほど青風という青年が言ったものと同じだった。
「青風が言ったとおり、あなたの持つ『煌玉』を私達に貸して欲しいの」
その言葉に高志は再び警戒色を強める。
「一つ聞く。その『煌玉』って何なんだよ」
「やっぱりダメじゃないか」
「名乗ればうまくいくと思ったんだけどなぁ……」
高志はマイペースな二人にだんだんと苛ついていく。
「真面目に答えろ!」
「『煌玉』と言うのは、自然の力を封じ込めた石の事だ」
青風は視線をエアから高志に移しながらそう言った。
「自然の……力?」
「そう、『大地』『火』『水』そして『風』……これらを封じ込めた4つの石の総称」
「まさか……」
高志は無意識のうちに手を胸元のペンダントに触れた。
「君の持つ『煌玉』は恐らくペンダントだと思うが……」
「!!」
「やはり気配通り、君は『大地の煌玉』の守護者のようだな」
青風は一歩前に出た。
「お前達は一体……」
高志は一歩下がる。
「今は理由は言えないが、とにかく君の持つ『煌玉』を貸して欲しい。
決して悪いようにはしない」
「そんな都合のいい話、信じられるか!」
高志はさらに後方へと引くと、右手を地面につけた。
「大地の牙!」
その叫びと同時に青風とエアの足下から、文字通り先端がとがった牙状の山が瞬間的に現れた。
間一髪、二人は左右に分かれ避けるが、それぞれが降り立った場所で再び同じように牙状の山が現れる。
それはまるで二人の狙うかのように周囲の商店街をも巻き込んで次々と現れていった。
気づいたときには天井のアーケードすらも突き破り、辺りは悲惨な状況となっている。
「金剛牙陣か……」
「お願いだから、私達の話を聞いて!」
「聞けるか!」
高志は明らかに冷静さを欠いていた。
今まで経験したことないようなプレッシャーと恐怖が、それを失わせてしまったのかも知れない。
「無駄だ! 牙から逃げることは出来ない!!」
「確かに地上にいる限りはそうかも知れないな」
牙を避けながら左右に移動している青風はそうつぶやいた。
そして次の瞬間、彼の姿が消えた。
いや、彼だけでなくエアの姿も消えた。
「!?」
高志は慌てて周囲を見回す。
だが、二人の姿は何処にもなかった。
「どこにいった!」
「上だよ」
その声に高志は上を見た。
牙が突き破ったアーケードに空いた穴から覗く星空。
その上空で二人がジッと見下ろすように立っていた。
「なっ!」
「確かに金剛牙陣は地上はおろか地下からの侵入者に対して絶対の力を見せる、『大地』の攻防一体の技。
だが唯一の死角である空からの攻撃に対して防ぐ手だては無い」
そう言うと青風は文字通り目にも止まらぬ動きで高志の目の前に現れる。
その突然の事に高志は動くことが出来なかった。
「そして、守護者の半径3m以内にも自分の身を守るという理由から作ることは出来ない」
そう言うと青風は彼のみぞおちに右手を当て『気』を体内に直接たたき込んだ。
「!!」
高志は一瞬大きく目を開き、そして青風にもたれ掛かるように倒れた。
「殺してないよね」
青風の背後に降り立ったエアが心配そうに高志をのぞき込む。
「そんな真似はしないよ」
彼はそう言いながら高志の首からペンダントを抜き取る。
それが自分たちの探し求めているものだと確認するとエアに預けた。
「これで一つ目……だね」
「ああ」
二人は高志をノルンの裏口に置くと、姿を消し結界を解いた。
すると先ほどの戦闘で破壊されたはずの建物などが何も無かったかのように元に戻り、商店街を往来する人たちの声が聞こえてきた。
それから数分後。
高志は戻ってくるのが遅いと心配して探しに出ようとした卯月によって発見される。
<あとがき>
恵理「……へ?」
絵夢「どうしたん?」
恵理「何があったの?」
絵夢「ありのままだけど」
恵理「だって……前半と後半にあまりにもギャップが……」
絵夢「ようやく物語が動き出した証拠」
恵理「でも……鷹代さん、大丈夫なの?」
絵夢「青風が大丈夫って言ってるから大丈夫でしょう」
恵理「あ、それ」
絵夢「どれ?」
恵理「その青風とエアって言う二人組。誰なの!」
絵夢「それはこれからのお楽しみ」
恵理「またそれなのぉ」
絵夢「またそれなの」
恵理「う〜〜〜〜」
絵夢「ではまた次回もお楽しみに〜」
恵理「う〜〜〜〜〜〜〜〜」

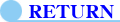
![]()
![]()