
ここは夢園荘LastStory
BEGINNING
第3話
桜が舞う春。
駅前のベンチで恵理は迎えを待っていた。
早瀬夫妻と過ごした2年間でいくらか表情が軟らかくなったように見えるが、実際は心を未だに閉じているようだ。
ロータリーの中央にある時計台で時間を確認すると、視線を下に落とした。
「……遅い」
そうつぶやいたとき、足下の自分以外の影に気づいた。
そして顔を上げると、写真だけでしか見たことがない青年−夏樹がそこにいた。
恵理はジッと彼の顔を見つめた。
「遅れてごめんな」
「………」
「あ、やっぱ怒ってるか……30分も遅れたからな」
「………」
「本当にごめん」
「………」
「樋山恵理ちゃんだよね」
「………」
「……あの?」
「不思議な人……」
「?」
恵理は表情や言動からその人の考えてることが分かる。
だけど、夏樹のそれは一切分からなかった。
むしろ彼の表情そのものが作り物のように思えてならなかったのだ。
そのことが彼女にとまどいを感じさせていた。
「不思議と言われても困るが……」
「だって、本当の表情じゃない」
「……」
夏樹は軽くため息をつくと彼女の横に座った。
「親父から変わった娘だとは聞いてたけど……そういうことか……」
「……」
「たしかに君の言う通りかもな。だけどそれは君にも言える事じゃないのか?」
夏樹のまっすぐと自分を見つめる眼差し。
それは冷たくも感じ、それ以上に悲しみを感じる。
「私は……」
「言いたくないことを話す必要はない。無理に聞きたくもないし……」
「……」
「とりあえず、これから同じ場所で暮らすんだ。お互い仲良くやっていこうよ」
恵理はコクッとで頷いた。
「そうすればいつかお互い、本当に笑える日が来るかも知れないしな」
「え?」
「親父から、君のことは『ショックな出来事があって笑顔を失った』と聞いてる。
でも実際会ってみてそれだけじゃ無い気がしたけど、それは別の話。
それに、だからといって君を特別扱いする気もない。あくまでも対等だよ」
「やっぱり不思議な人ですね」
「そうか?」
「誰もが聞きたがることを聞かないなんて……」
「君は話したいのかい?」
彼女は黙って首を左右に振る。
「だったらそれでいいんじゃないのかな。
誰だって触れて欲しくない心の傷はあるわけだし、無論俺にもあるし」
「そうですね」
「それじゃ、改めて自己紹介。
俺は君がこれから住むことになる夢園荘の管理人、早瀬夏樹。よろしくな」
「はい、私は樋山恵理。これからどうぞよろしくお願いします」
「こちらこそ」
夏樹は恵理に右手を差し出した。
「?」
「握手だよ。『はじめまして、よろしく』ってね」
「あ、はい」
その瞬間、恵理は少しだけ顔をほころばせ、夏樹と握手を交わした。
「やっぱり樋山さんって笑うと可愛いんだ」
「え!?」
「今、少しだけ笑ったよ」
「私が……笑った?」
恵理は信じられない様子で自分の頬に手をやる。
「私が……」
「ああ」
「あ……」
「?」
「今、管理人さんも笑いました。今のは本当の表情ですね」
「そうか?」
「はい」
お互い顔を見合って少しだけ笑みを浮かべた。
「そうだ、俺のことは『早瀬』でも『夏樹』でも良いから。
『管理人さん』って呼ばれるのはちょっとね」
「それでは『夏樹さん』と呼びますね。私のことも『恵理』でいいですから」
「わかった。
それじゃ恵理ちゃん、これから君の住む夢園荘に行こうか」
「はい、夏樹さん」
再び笑みを交わす二人。
ぎこちない笑みだがここからすべてが始まる、そんな予感を感じさせる笑みだった。
「そして本当に笑いあえるようになった俺達がここにいるわけだ」
恵理の話を聞いていた夏樹が口を開いた。
「そうですね」
「でもどうして話す気になったんだ?」
「夏樹さんの事はいろいろ聞いていたのに、自分の事は全然話していなかったことに気づいたの。
でもそれ以上に、私の事をもっと夏樹さんに知って欲しかったの」
「そっか」
「でも驚いたでしょ。小さいときの私、死にたがっていたことに……」
「そうだな……。何と言っていいか分からないけど、そう考えると俺ってずいぶんと無責任なこと言っていたなぁ」
「そんなことないよ。
あの時、夏樹さんが差し出してくれた右手で救われたから」
「そう?」
「はい。私に手を差し出してくれたのは夏樹さんとお義父様だけだし……」
「そう考えると親父に感謝か……恵理と巡り会わせてくれたんだからな」
「はい」
「しかし親父の奴も策士かもな」
「?」
「たぶん俺達がこうなると予測した上の行動のような気がする」
「まさか……でもそれあるかも……」
「今度会ったときにでも聞いてみればいいか」
「そう言えばお義父様とお義母様はまだ海外?」
「ああ、恵理をこっちによこしてからずっと向こうに居着いてるな。
電話では何度も話してるけど、実際に会ったのは……冬佳の葬式以来か?」
「それ……親子でもちょっと酷くない?」
じと〜っとした目で夏樹を見る。
「そう言わないでくれ。
結局、どちらが行くにしても旅費がかかるからな」
「それにしたって……」
「それに親父達がアメリカ支社で仕事しないで、本社で仕事してくれれば問題ないんだよな」
「確かにそれは言えるかも(^^;」
「だけどそれを言ったら恵理も同じだろ」
「私?」
夏樹の言葉にきょとんとする。
「恵理にとっても親父達は親だろ」
「あ、そうか……」
「あのなぁ」
夏樹は恵理の反応に少しあきれ顔になる。
「そう言わないでよ。
お義父様達と暮らしてた時も、それまでと同じようにあまり人と触れ合うことしてなかったんだから。
それにお義父様達も今みたいに『お義父様』『お義理母様』って呼んだこと無いし……」
彼女の生い立ちを考えると仕方ないことかも知れないが、恵理は当時のことを少し後悔しているようだ。
「でも私も夏樹さんと同じかな?」
「?」
「ここに来てから電話でしたか話したこと無いから……」
「そっか……」
短い沈黙。
夏樹はその雰囲気を断ち切るために明るく口を開いた。
「でもどのみち半年以内には親父達に会うことになるから良いけどな」
「半年以内?」
恵理は夏樹の言葉にちょっと首を傾げる。
そんな彼女の様子に夏樹は少し呆れた様子だ。
「あと数ヶ月で卒業だろ」
「うん」
「卒業したら前から言っているとおり……」
「あ……」
どうやら理解したらしい。
しかも顔が少し赤い。
「結婚……」
そう口に出すと、嬉しさのあまりちょっとトリップ気味になる。
「そうだよね〜。式にはちゃんと出てもらわないとね〜……」
何故かそこでぴたっと止まり、慌てて泣きそうな表情で夏樹に詰め寄った。
「夏樹さん、式場の予約とかどうしよう。
あれって最低でも半年前からしないといけないんでしょ」
「それは大丈夫だよ」
「え?」
「H・I・Bのコネでなんとでもね」
「そうなの?」
「まだ聞いた話なんだけど、夏に行った保養施設の近くに教会があるらしいんだ」
「本当に!」
「上手くいけばそこで出来るかも知れないと言う話なんだけど……」
「教会かぁ……」
彼女の頭の中はすでに結婚式になっているようだ。
「恵理?」
「白いウェディングドレス……夏樹さんと歩くバージンロード……」
「……(^^;」
この様子に夏樹は、恵理ってこんな性格だったかな?と彼女に対する認識を改めようかなと考えていた。
だがいつまでもこれでは埒があかないので、少し大きめの声で名前を呼んだ。
「え、なに?」
「だから一度ちゃんと見に行った方が良いかも知れないけどな」
「そ、そうだね」
トリップした自分に気づいて少し恥ずかしそうだ。
「それじゃあ、冬休みにでも行ってちゃんと話しまとめようか」
「うん!」
嬉しそうに笑う恵理。
それに答えるように夏樹も笑顔で返した。
<あとがき>
絵夢「3話かけての墓参りです。ラスト付近の恵理はちょっと妄想気味です」
恵理「でも分かるなぁ……好きな人との結婚……」
絵夢「こちらの恵理もトリップしてしまったようです」
恵理「私も彼氏欲しいなぁ……ねぇマスター!」
絵夢「その予定はありません」
恵理「が〜〜〜ん……マスターの意地悪〜〜……いじいじ……」
絵夢「と言うわけで次回からいよいよ物語が動く……といいなぁと希望的観測にのせてお楽しみに〜」
恵理「いじいじいじ………」

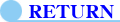
![]()
![]()