
ファンタシースターオンライン
『銀の光』
第3話 『探さない方が良いのかなって』
ナツキと別れた後、ハルカはハンターズギルド本部内の室長室で仕事をしていた。
すると机の隅に埋め込まれている電話機が鳴った。
ハルカはボタンを押し出ると秘書のユーリがモニターに出る。
「フローラ室長、スライダーさんがそちらに向かいました」
「ナツキが? ええ、分かったわ」
「それでは失礼します」
「はい」
ハルカがスイッチを切ると同時にナツキが部屋に駆け込んできた。
そしてツカツカと足音を立てて近づくと、机に両手をバンと叩き付けてハルカに迫る。
「ハルカ、すぐに調べて欲しいの!」
「どうしたの?」
「いいから!! 今から言う特徴の人をパイオニア1も含めた全ての中から検索して欲しいの!!」
「パイオニア1も? 少し時間が掛かるわよ」
「時間が掛かっても構わないから! ……緊急なの」
ナツキは急に声のトーンを落として俯く。
その様子にハルカは軽く溜め息をつくと「仕方ないわね」と言って、検索キーの入力の準備をする。
「ハルカ、ありがとう……」
「お礼は検索が完了した後で良いから。それで特徴は?」
「調べて欲しいのは2人の男女。男の方は名前は青風・フィールド。身長が180cmぐらいで藍色の腰まで届くぐらいの長髪。女の方は名前はエア・フィールド。身長が150cmぐらいで彼女も藍色の長髪。2人とも兄妹みたいにそっくりで街を歩けば絶対に誰もが振り向くような美青年美少女なの。私にとって自慢の兄さんと姉さんだよ」
「兄さんと姉さん?」
「うん。実の兄や姉じゃないんだけど、幼い私を拾って剣を教えてくれた人達なの」
「いわゆる師匠という事?」
「そう言うこと」
「それで年齢は?」
「年は知らないけど……見た目17歳と15歳ぐらいかな?」
その言葉にハルカは入力の指を止める。
「ちょっとまって。あなたがその人達から剣を学んだのは何年前の話?」
ナツキはなんでそんなことを聞くんだろうと首をかしげながらも数える。
「えっと5歳の時から10歳までの間一緒だったから……33年……」
そこでナツキはピタッと止まる。
「ナツキ?」
ハルカは急に黙ったナツキにどうしたのかと声をかけると、彼女はつぶやくように言葉を発する。
「……なんで2人ともあの時と全く同じ姿だったの?」
「?」
「ごめんハルカ……全部キャンセルして……」
「どうしたの?」
「ううん、なんでもないから……仕事中にごめんね……」
ナツキはそう言い残すと来たときとは正反対に肩を落としゆっくりとした足取りで部屋を出て行った。
ハンターズギルド本部内にある訓練場では、現在10人ほどのハンターズが訓練に汗を流している。
ある者は愛用の武器を振るい技の確認、ある者達は互いに剣を交わし腕を確か合い、ある者は射撃場で銃の訓練と言った風に各々がさらに強くなろうと頑張っていた。
そんな中にナツキはゆっくりとそこに足を踏み入れ、中央付近の空いている場所で足を止める。
その場にいた者達はその姿に気づき腕を止め彼女を見る。
マスコミの取材攻勢が過ぎ去ったとしても、彼女が有名人であることには変わりない。
そして先に訓練場にいた彼らはハンターズとして盗める技術は自分の物にしようと彼女の動きに注目するのは当然の事だろう。
さらにガラスで仕切られて向こう側にある休憩所にいる人達も注目している。
ナツキはしばらくジッとしていると両肩のアーマーから二本の柄をそれぞれ抜き銀色の光の刃を放出する。
右手にダブルセイバー・左手にセイバーと言ういつもの形だが、今までのフォトンの光とは違う銀色の光に周りで見ていた者達から驚きの声が上がる。
彼女はそんな声に耳を貸すことなく、仮想敵を相手に剣を振るい始めた。
出会いは5歳の時だった。
両親を亡くして1年。
父の知人の教会で過ごしていた。
幼いカナタはどうしても強くなりたい、早くハンターズになりたいと思い続けていた。
そしてある日。
一人で教会から離れた所にある公園で散歩をしていたとき、目の前を歩く2人とも藍色の長髪をしているカップルが目に入った。
男のベルトには二本のセイバーの柄が下がっている。
カナタはどうしてもそれが欲しくて、男に体当たりをしてバランスを崩した隙に一本盗んでいった。
そして追いかけてくる2人から逃げるために角という角を曲がって走り続けた。
10分ほど走ったところで姿が見えなくなり、カナタは安心して建物の影に隠れるように座り込む。
そこで息を整えながら、今盗んできたセイバーの柄を見ていると急に暗くなった。
見上げると、そこには全く知らないいかにもごろつき風の男が2人が立っていた。
「ガキがずいぶんと良い物持ってるじゃねぇか」
「おい、そいつを俺達によこしな」
男の一人がそう言いながらカナタが抱きしめるセイバーに手を伸ばしてきた。
カナタは盗られまいと「嫌だ!」と叫んで背中を向ける。
「威勢が良いねぇ」
そう言うとカナタの襟元を掴んで持ち上げた。
「離せよ!!」
カナタはじたばたと暴れるが、5歳の子供に何が出来るわけもなく必死に抱きしめていた柄をいとも簡単に盗られてしまった。
そして男達はカナタを捨てるようにその場に投げ捨てた。
するとその時、カナタを守るように藍色の髪を持った少女がカナタの身体を抱きしめて守った。
「え?」
カナタは何が起きたか分からないまま、その少女の顔を見上げる。
「大丈夫?」
少女はニコリと微笑んで聞いてきたので、カナタは驚きを隠しながらぎこちなくコクと頷く。
その少女はさっき自分がセイバーを盗んだカップルの片割れだったからだ。
だが少女は気にする風でもなく嬉しそうに微笑む。
「へぇずいぶんと可愛い娘だね」
「そんなガキを放っておいて俺達と遊ばないか?」
先ほどの男達が彼女に話しかけると少女はいかにも嫌そうな顔をする。
「あなた達の相手は私じゃないわよ」
「お前達の相手は俺がしてやるよ」
少女の言葉尻を取るように男性の声が男達の後ろから聞こえた。
男達は振り向くとそこには藍色の髪をした青年が立っていた。
カナタはその姿に思わず口を押さえて声が出ないようにする。
彼女がいるんだから男もいて当然と言えば当然なのだが、本当にいるとは思ってもいなかったようだ。
そんなカナタの思いをよそに目の前の出来事は進行していく。
「なんだてめぇは!?」
「ちんぴらって奴の言葉は何処の世界でも同じなんだねぇ」
青年はやれやれと首を振る。
「何だと!!」
「とりあえずそこにいる2人の知り合いでね。その手に持っているのを置いて帰って欲しいんだけど」
「ふざけたこといってんじゃねよ」
「どちらがふざけてるのかな?」
「うるせえ!」
セイバーの柄を持ってない方が殴りかかる。
だが青年は軽く拳を避けると、腹部に右フックをたたき込みいとも簡単に倒した。
「ふざけやがって……」
セイバーの柄を持つ方が後ろにいる2人に向かって、そのフォトン射出口を向ける。
「一歩でも動いてみやがれ。2人の命はねぇぞ」
「やれやれ……やりたかったろうどうぞ」
「なっ!? 俺は本気だぞ!!」
「だからどうぞって言ってるだろ」
「そうそう、やっちゃってくださいよ」
藍色の髪の少女も一緒になってはやし立てる。
少女の腕の中にいるカナタは自分の耳を疑うが、笑いながらはやし立てる2人に焦る。
もしもの時は、このまま放り出されて私はこいつに殺されてしまうのでは無いだろうかと……。
「心配しなくても大丈夫だよ」
カナタの焦りに気づいたのか少女は耳元でそっと囁く。
その言葉に何故か本当に大丈夫のような気がしてきた。
初めて会う人、しかも自分がセイバーを盗んだ相手なのに……。
そして目の前にいる男をちゃんと見た。
「貴様らぁ後悔すんじゃねぇぞ!」
男は追いつめられた獲物のように脂汗を流しながら、セイバーのスイッチを押す。
カナタは一瞬目を閉じるが、いつまで経っても何も起きないので目を開けると、何度もスイッチを押しながらセイバーの柄を振っている男の姿が目に入った。
「な、なんで出ねぇだんよ! この不良品が!」
一向にフォトンの刃が出ない事に焦りセイバーの柄を青年との中間の地面に叩き付けた。
いや、正確には叩き付けられる瞬間、青年は目にも止まらぬ動きでその柄を拾い上げ、純白の刃を放出しその剣先を男の首元に突きつけた。
「な……なんで……」
いくらやっても刃を出すことが出来なかったセイバーを青年が簡単に出したことが信じられないようだ。
「こいつは特別製でね。お前のようなちんぴらに扱える代物じゃないんだよ」
青年は不敵な笑みを浮かべながら言葉を続ける。
「このまま喉を貫かれるが良いか、それともおとなしく去るか好きな方を選べ」
剣先がのど元の皮を焼き嫌な匂いがする。
「わ、わ、分かった。ゆ、許してくれ」
「だったらそこに転がっているゴミと一緒にとっとと消えな」
先ほどまでの軽い調子とはうって変わったドスの利いた声に男はまだ気を失っている男を担いで逃げ出していく。
その後ろ姿を見送ると青年はセイバーの刃を消し腰のベルトに下げた。
そしてカナタの方を見るとゆっくりと近づき腰を下ろして視線を合わせる。
カナタはその場から逃げ出そうとしたが少女がしっかりと捕まえているために逃げ出すことができない。
「さて、どうして盗んだのかな?」
青年は優しく聞いてくる。
「強く……なりたいから……」
「?」
青年は少女と目を合わせ首をかしげる。
「強くなりたいの! 死んだお父さんやお母さんみたいに強くなりたいの!」
怒鳴るように言うカナタの言葉に2人は納得したように頷いた。
「だからといって盗むというのはどうだろうね。それじゃ両親は悲しむだけだよ」
青年は優しい口調で諭すように言う。
「本当に強くなりたいのだったら、今はたくさんのことを勉強しないとね。何が正しくて何がいけないことなのか。少なくとも人の物を盗むと言うことはいけないことだよ。そう言うことややっていたら強くなんか絶対になれないよ」
青年の言葉にカナタは唇を噛み締め涙を堪えて聞いている。
「ねぇ、あなたの名前は何て言うの?」
少女が頭の上から聞いてきた。
「カナタ……カナタ・トラッシュ……」
「カナタちゃんって言うんだ」
少女は片手でカナタの頭を撫でながら青年に聞く。
「ねぇ、この娘も反省しているようだし、どうしようか?」
「そうだな……なぁカナタ」
青年に名前を呼ばれてパッと顔を上げる。
「こいつを持ってスイッチを入れてみろ」
そう言いながら青年はカナタの右手に持っていた柄を持たせた。
カナタは恐る恐るスイッチを入れてみる。
すると射出口の中に小さな光の点が見えた。
「すごいね」
少女の言葉にカナタは首をかしげる。
青年は光の点を見つめながら少し考えてカナタに聞く。
「俺達と一緒に来るか?」
「え?」
「だから、剣を教えてやるよ」
「本当ですか?」
カナタは青年の思いもよらない申し出に嬉しそうに何度も聞き返す。
仕舞いには青年も少女も苦笑を漏らしてしまうほどだった。
その晩、カナタは書き置きを残して青年達−青風とエアと共に修行の旅へと出た。
1時間を経過してもなおナツキの仮想敵との戦いは続いていた。
その様子は周りの者達の目には可憐に舞っているように見えていた。
さらにその銀色の髪と銀色の三つの刃が天井から降り注ぐ照明に反射して神秘的なものにも見える。
そんな周りの反応をよそにナツキは剣を振るいながら思い出していた。
どうして自分はあの時2人の姿が変わっていないことに気づかなかったんだろう。
そして2人の言葉の意味。
『私達は時間に支配されていないから……』
……それは永遠に年をとらないと言うことなの?
『もともと俺達はパイオニア1にも2にも乗っていないからな』
……それじゃどうやってラグオルに来たの?
もしかして2人は偽物なの?
……でもそれはない。そうだったらこの剣は使えないはず。
だったら……。
どうして?
どうやって?
なんで?
もしかして……。
だけど……。
………わからないよ。
ナツキは答えの出ない迷路の中を彷徨い続けていた。
カナタが青風達と行動を共にして5年の月日が流れた。
長いようで短い5年。
この間に青風とエアは剣を始め2人が教えることの出来る全てのことを教えた。
そして10歳になったカナタは見た目はまだまだ年齢通りの子供だが、その腕と知識は一般のハンターズ並の物を持つに至っていた。
3人は今カナタが過ごした街のすぐ側の丘の上にいた。
「兄さん、どうしてここに?」
「明日この街のハンターズギルドで登録試験が行われる。だから来たんだ。前にも話したと思うがこれからお前は一人で生きていかなければ行けない。そのためにはライセンスは必要だ」
「…………」
「怖いのか?」
「怖くないです。ただ……寂しいだけです」
「正直だな」
「あと心配なことが……ライセンスが取れるのかなって」
「カナタはライセンスはいらないの?」
エアがカナタの顔をのぞき込むように聞く。
「ライセンスは欲しいです。でも……」
カナタはそのまま俯く。
「どうしたの?」
「まだ10歳だから……」
「カナタなら大丈夫だよ」
「だけど……」
自信の無い言葉に青風は、カナタの髪をぐしゃぐしゃとかき混ぜる。
「に、兄さん、止めてくださいよ」
カナタは抗議の言葉と共に青風の手を退けようとする。
「お前がそんなことを言うからだ」
「でも……」
「自信を持てよ。今のお前の実力なら簡単に取れるさ。それとも俺達の言葉が信じられないのか?」
「そう……かな……」
カナタは顔を上げて街を見る。
その横顔に青風はベルトからセイバーを取る。
「カナタ、これを持ってみろ」
「あ、ハイ!」
カナタは慌てて受け取ると、スイッチを入れてみる。
5年前に比べて光の玉が大きくなっただけで、剣にはまだまだほど遠い物であった。
「……ダメでした」
カナタは肩を落として青風にそれを返す。
青風はカナタからそれを受け取ると、彼女の視線まで腰を下ろし目を見る。
「こいつはずっと話してきたとおり『心』の力を変換して剣となり武器となる物。心が強ければ強いほどこの世界にあるどんな武器よりも強力な物になる。そしてその逆ならばただの金属の棒に過ぎない。お前はこれからハンターズとなって一人で様々な場所に行き、様々な人と出会い、様々な経験をすることになるだろう。その中で心を磨け。心技体と言う言葉がある。お前には教えられる全ての技を教えた。身体も成長と共にさらに強くなるだろう。だがそれらには限りという物がある。年を取れば絶対に技も身体も衰えるからだ。しかし心は違う。心には限度は無い。強くなれ」
青風の言葉にカナタは力強く頷く。
そしてそれに対して青風も頷き返すと、もう一つダブルセイバーの柄も取り、二つの柄をカナタに見せる。
「これらが使いこなせたら、卒業の証としてお前に渡そう」
「本当ですか?」
「ああ、だからハンターズとしてしっかり修行してこいよ」
「ハイ!」
翌日カナタは一発合格でライセンスを取得することになり、ハンターズとしての日々が始まる。
2時間近くに渡る剣の舞を止めたとき、どこからともなく拍手が聞こえてくる。
ナツキがそちらの方を向くと携帯端末を持って微笑むハルカが立っていた。
「ハルカ……」
「おつかれさま、少し良いかしら?」
ナツキは小さく頷くとハルカと共に訓練所を後にした。
再び本部内の室長室に戻ってくると、部屋の中央の応接セットに向かい合わせに座るとテーブルの上に端末を両方から見えるように置いた。
「ここで話すなら持ってくる必要なかったんじゃないの?」
「訓練場の横の休憩所で話そうかと思ったんだけど、ナツキのギャラリーが多かったから」
「ああ……なるほど……」
ナツキは訓練場から出て行くときの様子を思い出して納得したようだ。
何と言っても拍手で見送られたのだから。
「もしかしたらしばらく訓練場に行きにくくなったかな?」
「気にしなくても大丈夫だと思うけど……どうかな?」
大げさに溜め息をつくナツキにハルカは笑いながら慰めの言葉をかける。
「ところでナツキ……さっき使ってたあのセイバーは何? 銀色のフォトンなんて見たこと無いんだけど……」
「ああ、これ?」
そう言うとナツキは右肩からセイバーを取り出してハルカに見せる。
「持って良い?」
「うん」
ハルカはナツキから受け取るとまじまじとそれを見る。
「見た目は普通のセイバーと変わらないようだけど……あれ、これどこからフォトンエネルギーを供給するの?」
彼女は本来あるはずの供給口が無いことに気づき、色々と廻したりのぞき込んだりする。
「そういうのは無いよ」
「え?」
「だってそれは兄さんが作った物で、『心』の力を剣にする物なの。そして心の色をそのまま剣の色になるという物」
「……『心』って……何それ?」
「いや、だからそのままだって」
「そんな……」
「とりあえずスイッチを入れてみて」
「……う、うん」
ハルカは不信感丸出しで放出口を横に向けてスイッチを押す。
すると先端部分で半透明の小さな輝きが灯った。
「うわ、すご〜い」
その光を見てナツキは驚きの声を上げる。
「え……?」
理由が分からないハルカはジッとその光を見る。
「それがハルカの心の色。ただ力が弱いからその程度なんだよ」
「はぁ」
ナツキの説明にハルカは曖昧な返事をする。
そしてスイッチを切るとナツキに返した。
「でもただ単にフォトン不足とかじゃないのかな」
そのハルカの呟きを聞いたナツキは無言で銀の刃を放出した。
そして「ねっ」と笑顔でハルカの驚き固まる顔を見る。
その後、ナツキが剣を収納した後もしばらく納得出来ない様子でハルカは複雑な表情をしていた。
「ところで何か用事があったんじゃないの?」
「え、あ……そうそう。さっきの検索が終わったのだけど……」
「いたの!?」
ナツキは身を乗り出してハルカに迫る。
「一応、藍色の長髪と17歳前後の男性と15歳前後の女性、それからそれぞれの身長で検索してみたの。ちょっと確認してもらえるかな?」
「あ、うん」
ナツキは座り直すと端末に表示される顔写真付きのデータを見ていった。
そして3時間後。
ナツキは疲れたようにモニターから目を離し背もたれにもたれ掛かった。
「やっぱりいない……」
「そう……」
ナツキがモニターを見ている間、仕事を片づけていたハルカは顔を上げ、残念そうな表情でそう言った。
「どうする? 検索キーを変えて調べ直しみる?」
「いいよ……」
「だけど、ナツキにとって大切な人達なんでしょ」
「だからこそ探さない方が良いのかなって思う」
「え?」
ナツキの不可解な言葉にハルカは首をかしげる。
「だから知らない方が良いこともあるって事」
「本当に良いの?」
「うん」
ナツキはそう返事をすると立ち上がり背伸びをする。
「正直に言うとどちらにも乗って無くて良かったと思っているの。どちらに乗っていてもあまり良い結果は出ないと思うし……それでもたとえ幻だとしてもここにこうして兄さんの剣があるという事実は変わらないしね」
「ナツキがそう言うなら良いけど……私もあなたに剣を教えた2人に会ってみたかったかな」
「機会があれば会えると思うよ」
「だと良いけど」
「それじゃ私は行くね。仕事中にありがとう、ハルカ」
「ええ、またね」
ナツキはハルカに簡単に挨拶をすると室長室を後にした。
ギルド本部を出たところでナツキは洞窟で襲われたと事を言うのを忘れていたことを思い出した。
「ま、いいか……余計な心配させても仕方ないしね」
そうつぶやくと、駐輪場に停めてあるホバーバイクに跨り自分の部屋に向けてエンジンをかけた。
<あとがき>
絵夢「とりあえずこれで前半は終わり」
恵理「もうお終い?」
絵夢「前半がね」
恵理「ああ、なるほど」
絵夢「次回はインターバルで、その次から後半の予定」
恵理「と言うことはクライマックスも近い?」
絵夢「近いね。今回は一話が長い分話数が短くなりそうだよ」
恵理「そうだよね。今までの1.5倍ぐらい書いてる?」
絵夢「そのぐらいかな? 調子にのっているっぽいけどね」
恵理「あはは」
絵夢「そう言うわけでまた次回もどうぞヨロシクです」
恵理「皆さん次回までまったね〜〜♪」

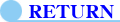
![]()
![]()